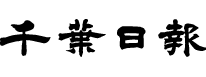新型(しんがた)コロナウイルス感染症(かんせんしょう)のあつかいが5月8日から変わりました。感染症法という法律(ほうりつ)(国のルール)で、インフルエンザやはしかなど、古くからある、おなじみの感染症と同じ「5類」という区分に引き下げられたのです。
これまでは「新型インフルエンザ等感染症」という特別な区分でした。流行をおさえるために、国や自治体が国民に「こうしてください」といろいろと求めてきました。しかし5類になると、対策(たいさく)は一人一人が自ら決めるのが基本(きほん)になります。
5日には世界保健(ほけん)機関(WHO(ダブリューエイチオー))が、2020年から約3年3カ月続いた新型コロナの「緊急事態宣言(きんきゅうじたいせんげん)」を終わりにすると発表しました。日本でも世界でも、コロナを特別あつかいしない日々が始まったと言えます。
さて、コロナが5類感染症になると何が変わるのか、主な例を見てみましょう。まず流行の大きさを知る方法です。これまでは、感染が分かった全員の数を国がまとめて毎日発表していましたが、今後は一部の病院から報告(ほうこく)された人数が週1回だけ発表されます。
感染した人への対応(たいおう)も8日からは、国や自治体が「外出しないで」などと求めることはできず、本人がどうするか決めてよいことになりました。
ただ、多くの子どもが集まる学校の中は感染症が広がりやすいので、コロナにかかった子が学校を休む「出席停止(ていし)」の日数が引き続き決められました。これまでは原則(げんそく)として7日間だったのが原則5日間になります。ただし出席するには、具合が良くなってから1日たっていることも必要です。
感染した人に対応する病院をこれまでより増(ふ)やすほか、ワクチンも23年度は引き続き無料で接種(せっしゅ)できるようにしました。(吉本明美)