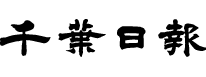2024年11月3日 05:00 | 有料記事

ハナイソギク=2007年12月17日、千葉市(初芝清氏撮影)

サトイソギク=2007年11月8日、千葉市(初芝清氏撮影)
イソギクは磯菊の意で大房岬などの岩場などに生えている。
飯泉優『草木帖-植物たちとの交友録』(2002年、山と渓谷社)に「分布は房総半島から浜名湖付近までの海辺に限られているが、本来は四国の太平洋岸に自生するシオギク(潮菊)から進化した種類と考えられている。(中略)ふつうは筒状の小花だけが多数集まって、直径6ミリほどの頭花をつくるが、ときに周辺部に黄色の舌状花をつけるサトイソギク(里磯菊)や白色の舌状花をつけるハナイソギク(花磯菊)が見られる。これは大昔の古い形質がひょっこり現われる先祖帰りの現象と考えられているが、栽培菊との間の自然雑種だという説もある。葉は厚く、表面は銀白色でつやがあり、輝くような感じだ」とある。
人々は花に注目して短歌や俳句に詠んでいる。葉、つぼみ、花、香り、 ・・・
【残り 660文字】