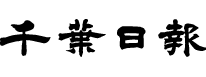2023年8月20日 05:00 | 有料記事

タカブシギ シギ科 全長21・5センチ。ヨーロッパから極東地域で繁殖。冬期には南に渡る。主にアフリカから南アジアで越冬する。体の模様がタカの斑紋に似ていることからこの名がある。県重要保護生物=2008年2月14日、木更津市(筆者撮影)

タカブシギ 県北部に記録が多い=2016年1月16日、木更津市(筆者撮影)
秋晴れの日、ハスの大きな葉が風で揺れてガサガサと音がする。あぜのアカマンマの赤い花が美しい。ハス田を一回りしたが、撮りたい鳥がいない。「帰ろうか?」と思ったが、車が1台止まっていて、女性がカメラを持って座席に座っていた。
「何かいるのかな?」と思った。彼女が去ったあと、よく見ると「あ!いた」。小さなシギが泥に長い口くちばしを頻繁に差し込んでいる。大きさは、ムクドリより一回り小さい。小さな円い眼、長い黄色の脚、暗褐色の背に白い斑点。「タカブシギ!久しぶり」とうれしくなった。背の色が、あぜの泥の色とそっくり。気づかないわけだ。
ひとしきり、えさをあさっ ・・・
【残り 1026文字】