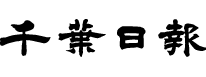旭市を拠点に広域的な医療を担う「地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院」が開院70周年を迎えた。1953年に「地域住民の健康を守る」と発足し、医療ニーズに応えながら診療科目を拡大。千葉県東部と茨城県南部を含む旭市から半径30キロ圏(人口約90万人)を診療圏とする国内有数の規模を誇る自治体病院に成長した。人口減少や高齢社会、新たな感染症の流行など時代の変化が激しい中、24時間対応の救急医療を核とした広域型急性期基幹病院として、どのように発展を続けていくのか。同院の吉田象二理事長と野村幸博病院長に話を聞いた。
◆「断らない救急」軸に発展
―旭中央病院は、どのように誕生したのですか。
吉田理事長 第2次世界大戦後の地方には医療機関が少なく、「地域住民の健康を守ろう」と当時の旭町のほか8町村による一部事務組合立の国保病院として1953年3月1日に開院しました。敷地面積は6600平方メートルで、病床数113床、診療科目4科、職員45人でした。
初代病院長の諸橋芳夫(1919~2000年)が「救急は地域医療の原点」と救急患者を断らずに受け入れたことで診療圏が拡大し、受診者が増えました。現在の診療圏は県北東部、茨城県南東部など病院を中心とした半径30キロ以内と広く、診療圏人口は約90万人に上ります。患者にとって、すぐに診察してくれる病院が1番。1954年に独自に救急車を購入するなど急患の受け入れ体制を整えました。車社会の到来で遠方からの患者が増えた一方、交通事故による救急搬送も増え、治療するために脳神経外科を70年に開設しました。生活が豊かになり、高齢社会になった現在は生活習慣病が増えています。
野村病院長 諸橋・初代病院長は地域医療への情熱にあふれ、有言実行のカリスマ。時代の先を読む力を発揮して診療科目を増やしていきました。地域の病院から基幹病院に発展し、広域型急性期基幹病院となり、2017年から地域医療支援病院の役割を果たしています。23年9月1日現在、敷地面積は19万3080平方メートル(開院当時の約30倍)、診療科目は40科(同10倍)、常勤職員数2210人(同約50倍)と大きく成長しました。
◆自治体立病院で最大規模
―全国有数の規模を誇る旭中央病院の特色などについてお聞かせください。
吉田理事長 5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)、4事業(救急医療、災害時医療、周産期医療、小児医療)全てで地域の拠点病院。全国で900超ある自治体立病院の中で、営業規模、診療実績ともにトップクラスです。
例えば2021年度の香取海匝2次医療圏における当院の疾患占拠率は52・7%に達しており、特に小児疾患は98・0%、婦人科疾患は93・2%と高い値になっています。また全国自治体病院協議会の医療の質の評価の公表資料(22年度)によると地域医療機関サポート率は93・0%(600床以上の基幹病院の平均67・2%)、地域救急貢献率は72・6%(600 床以上の基幹病院の平均 25・6%)、地域分娩貢献率は72・2%(600床以上の基幹病院の平均19・8%)となっており、診療実績の上でも地域医療支援病院としての役割を充分に果たしていることが証明されています。
また、県内4か所の「基幹災害拠点病院」の一つでもあり、東日本大震災(11年)で中心的な役割を果たしたほか、近年では19年の房総半島台風の際、当院にDMAT(災害派遣医療チーム)活動拠点本部が設置され、保健所と共同で地域の災害支援活動を実施しました。
「教育のない病院に発展性はない」というスローガンのもと、医療従事者の育成にも力を注いでおり、「臨床研修指定病院」(1981年認定)として年間約60人の研修医を受け入れています。附属看護専門学校(64年設立)ではこれまでに約2600人を輩出し、当院の医療の質向上に大きく貢献しています。新卒の看護師国家試験合格率は直近5年間のうち4年間で100%を達成しました。
野村病院長 「地域医療は実際にその土地に住まなければ分からない」と当院の近くに職員宿舎(医師297戸、看護師等334戸、看護学生48戸)を用意し、勤務する医師のほとんどが入居しています。諸橋・初代病院長の「病気は治って喜ばれ、不幸にして亡くなられてもそのご家族から良い病院を選んだと感謝される病院、更に死後剖検をさせていただき死因を究明し、医学医術の進歩に寄与し、医師の反省、研修の糧にさせていただく。また、ご家族に死因を正しくお伝えし満足していただく病院でありたい」の理念の下、剖検に力を入れています。
◆少子高齢化への対応も
―地域の医療ニーズに応えるため、さまざまな取り組みを進めていますね。
野村病院長 2019年に導入したドクターカーは迅速な救急医療の提供につながっています。
新型コロナウイルス感染症に対しても多くの患者を受け入れるとともに、感染症科、感染対策室を中心に病院全体で院内感染の予防や拡大防止に取り組んでいます。さらに地域の病院や介護福祉施設の感染対策にも協力しています。
医療の質の維持・向上へ、TQM(Total Quality Management)センターが患者満足度や、入院から退院までの治療・検査の計画表「クリニカルパス」の適用率などの算出と分析、質改善活動の推進、組織横断的活動を支援しています。
チーム医療の時代を迎え、職員が最大限の力を発揮できるように全体を見渡したマネジメントも重視しています。
吉田理事長 地域の高齢化率は上昇傾向にあり、人口減少が進んでいますが当院には産婦人科、小児科、新生児科、ハイリスク妊娠や高度な新生児医療に対応する周産期母子医療センターがあり、安心して出産・子育てできる医療を提供しています。若い世代に住んでもらいたいですね。 高齢者医療では、入院患者で介護が必要なケースが増加傾向にあり「地域包括ケア」のニーズが高まっています。今後、介護と医療の連携がより一層重要になると思います。
◆地域とともに歩む病院として
―今後の抱負は。
吉田理事長 来年から医師の働き方改革が始まります。近年の若手医師は都会勤務志向が強くなっていますが、医師の確保に尽力してこれまで通りの上質な医療サービスを提供します。
10月14日の70周年記念式典では「医療がつくる地方創生」をテーマにした講演があります。病院のステークホルダーの方々と一緒に今後の医療体制を考えるきっかけにしたいです。そして誰もが元気で安心して住めるまちを目指します。
野村病院長 高度急性期病院として専門診療をしてきましたが、今後は地域に密着した総合的な診察と両立したいです。例年夏休みに実施している高校生向け職業体験を70周年記念イベントの一環として行いました。300人超の応募があり医療職への関心の高さを大変うれしく感じました。病院は雇用の場でもあり、住民の健康を守るほか、地域経済の一翼を担えればと思います。